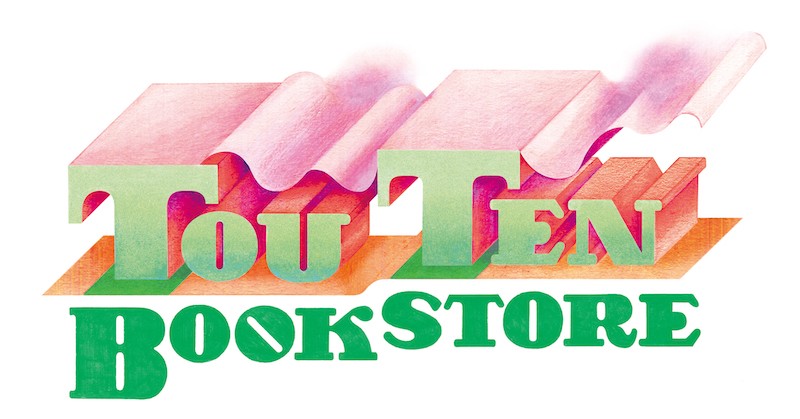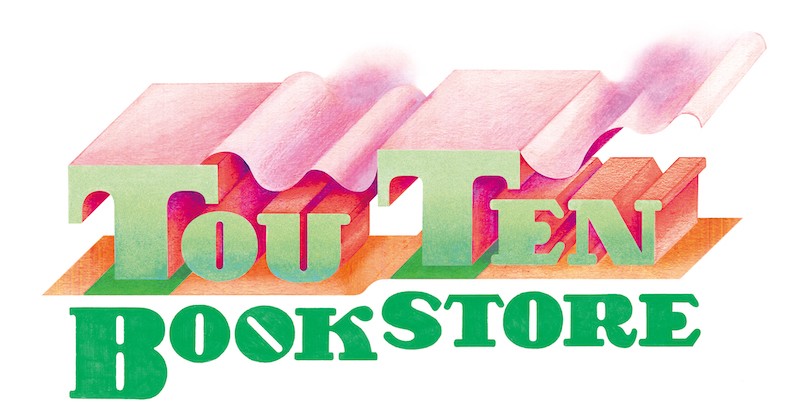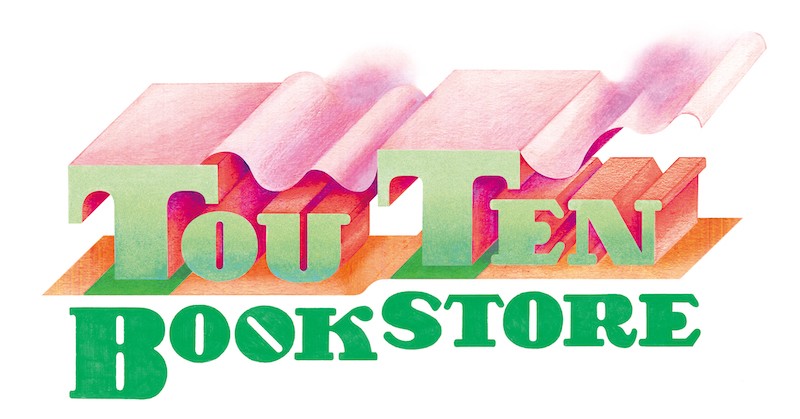TOUTEN BOOKSTORE NEWSLETTER #81
#81 INDEX
-
HELLO
-
TOUTEN ベスト (2025.4.14-2025.4.27)
-
新入荷&今週の1冊
-
イベント情報
-
AFTER TALK
🌬️HELLO
風が強すぎて店がガタガタ、近所の何かがカランカランと鳴っている。もうG.W.が始まっているんですね。今年は客足が少なくて店頭はのんびり営業で、月末の入金作業も余裕を持って着手しました。最近はなんだかんだ店頭以外の仕事も入り、当店の開店時より気にかけてくれていたMさんが住んでいてるマンションにあるライブラリの選書・納品をさせていただいたり、本チャンネルの収録を連続でしたりと地味に忙しい日々でした。
本チャンネルにて、4/21に発売した『線場のひと 下』のインタビューが公開されました。戦後日本とアメリカを舞台に上下巻で刊行。戦争/社会/国家の理不尽さを描きながら、それでも自分にとって大切なものを奪われないよう抵抗しながら生きていく人たちを描いた、素晴らしい漫画でしたのでぜひ、読んでほしいです。現代アーティストの小宮りさ麻吏奈さん、初著書の漫画。下巻の途中からはもう、登場人物たちが過ごしてきたその長い時間を想像して立ち尽くすみたいに読んでいました。歴史で描かれてきたものの周縁に置かれていたクィアな人たちの存在を、当たり前にいるのだということを示した作品です。
最近読むものが全て面白い。特に今、少しずつ読み進めている『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』が個人的に面白すぎる。私が取次時代から信じていた本屋ナラティブたちに、データたちがよっこらせとプレゼンを始める。「本を置けば儲かっていた時代」なんてなかったという事実には口から「がーん」という言葉がそのまま出た。(インフレ率に対して)本の価格も低くてマージンも低い、二重苦の構造。あと、元々、古本と新本を一緒にやる兼業本屋が多かったそうですが、昭和初期に本屋で買われた新刊をそのまま同じ店で買取り、取次に返品して現金化しちゃう不正が横行して古書店をやる人は新刊書店組合に入ることは禁じられたりとか、びっくりする話も多々。マルジナリア書店さんで開催された著者・飯田一史さんとのトークイベントも面白かったです。(アーカイブ配信は見当たらずでした。)日本でも書店振興として「書店振興プロジェクトチーム」なるものが発足されたけど、管轄は文化庁でもなく、文科省でもなく、経済産業省。その時点で文化政策としてではなく経済政策となっているという視点。フランスは文化政策だから市場に切り込んだ政策が打てるのだという話は納得。
📚TOUTEN BEST ( 2025.4.14-2025.4.27 )
・生きる力が湧いてくる(野口理恵 / 百万年書房)
"私はおそらく多くの人がもつ家族観をもっていない。おそらくこれからももつことはできない。"『USO』誌編集長にしてrn press社主・野口理恵さんのエッセイ集。特典小冊子付。野口さんの「版元日誌」を読んでいたので、個人的にも読みたいと思っていた新刊。「生きる」という言葉が立体になったような本で、「生きたい」と思わせてくれる本を今まさに書いてくれている、と思う。
・おめでたい人(寺井奈緒美 / 左右社)
"ああ、私はパーティーピープルになれるような明るい人間ではありません。でも、おめでたい人になりたい。どうか、おめでたく生きる力をください。"(「おめでたい人」より)歌人・土人形作家・エッセイストで『生活フォーエバー』著者・寺井奈緒美さんの新刊。ささやかでちょっと間抜けな暮らしをことほぐエッセイ&短歌28篇。
・アウト老のすすめ(みうらじゅん / 文藝春秋)
"アウト老(ロー)とは、はみ出し老人のことなり。大人げないまま新型高齢者となったみうらじゅんの珍妙な日常や妄想、愛のメモリーがてんこ盛り! 息苦しい社会に風穴を開ける珠玉のエッセイ集。"
・みえないもの(イリナ グリゴレ / 柏書房)
デビュー作『優しい地獄』の著者、ルーマニア出身の文化人類学者イリナ・グリゴレの最新作。娘たちと過ごす青森の日々。ふとよみがえる故郷ルーマニアの記憶。そして、語られてこなかった女たちの物語――。虚実を超えて、新たな地平を切り開く渾身のエッセイ。
・『随風』(書肆imasu)
文学フリマや独立書店の店頭を席巻する随筆/エッセイムーブメントに呼応する文芸誌、ついに創刊!執筆陣敬称略:宮崎智之、仲俣暁生、友田とん、早乙女ぐりこ、海猫沢めろん、オルタナ旧市街、ササキアイ、鈴木彩可、作田優、岸波龍、竹田信弥、柿内正午、横田祐美子、野口理恵、北尾修一、森見登美彦、円居挽、あをにまる、草香去来、西一六八
📚新入荷&今週の1冊
・ランバーロール 07(ランバーロール編集部 / タバブックス)
おくやまゆかさん、森泉岳土さん、安永知澄さんの漫画家3人が主宰を務める、漫画と文学のリトルマガジン[ランバーロール]07、特集テーマは「中年」。ナイステーマすぎる!そして一発目に藤岡拓太郎さんの短編入れるのも素晴らしい!いきなり爆笑してしまった!トータルで滋味深い1冊。
・私の小さな日本文学(チェ・スミン=編 / 夏葉社)
ソウルでひとり出版社「夜明けの猫」と、書店「セゴ書林」を営むチェ・スミンさんによる、これまでにない、あたらしい日本近代文学入門です。芥川龍之介、萩原朔太郎、伊藤野枝などの16編の近代文学の掌篇、装画は恩地孝四郎さん、長いあとがきはチェ・スミンさんが日本語で書いています。
・IN/SECTS vol.18 特集 THE・不登校(インセクツ)
"学校に行かないということがそもそもどのようなことなのか、不登校は後ろめたいことなのか、みんなにとって学校とは? などの考えるきっかけになればと、不登校児童の親、不登校経験者、学校の先生、そして、不登校児童を中心にいろんな人たちと話してみた。 さて、みなさんにとって学校って? 不登校とはどういうことなのか、一緒に考えてみましょう。"
・おかわりは急に嫌(古賀及子 / 素粒社)
"それくらい、日常というのは人に構ってくれないものだ。"
日記エッセイの書き手・古賀及子さんが、戦後日記文学の白眉とされる武田百合子『富士日記』のきらめく一節をあじわいながら、そこから枝分かれするように生まれてくる自身の日記的時間を綴る。
\📚今週の1冊📚/
名古屋駅西にある中華料理屋a.k.a.短歌の聖地「平和園」の小坂井大輔さんのセカンドアルバム的新刊!サイン入りで入荷しました。
町中華屋の長男として舞い降りたばかりにすべての床のぬるぬる
親でも見分けがつかないだろう宝くじ売り場の列に溶けるわたしは
断面がハートの形の青葱が止めどなく来てなんだ貴様ら
小坂井さんの日常なのか、はたまた想像なのかわからないけれど、その日常にある一瞬から想起させる物語のイメージや個人的な日常のシーン。面白いし、意表を突かれるし、刹那さを感じるし、だらっとそばにいることもある。1冊に閉じ込められたこの空気感をぜひ味わってほしいです。装丁は鷲尾友公さん。本が一つの美術作品になっています。
👀展示&イベント情報
【展示】【25.5.2-5.10】高重乃輔写真展「基地ができる」
"南西諸島の北端に位置する馬毛島では今、米軍も使用することが決まっている自衛隊基地の建設が進められている。その馬毛島から12キロ東の海に、祖父母が眠る種子島がある。今この時代に新しく基地を造ることについて、かつて戦争を体験した祖父母はどう考えていたのだろうか。ぼくはそれが知りたくて、種子島に通うようになった。戦争体験者の意思を想像し、国を守るとはどういうことかを考えた3年間の記録。"
イベント
出店情報【25.5.5】BOOKBOOK(リンクは金城市場さんのインスタグラムになります)
名古屋市北区清水シタまちエリアで開催される本のイベント「BOOKBOOK」に出店します。当店は金城市場に出店します!ぜひ遊びにいらしてください!
【25.6.14】「さいきまこさんと性暴力について考える」(主催:むちむち)
学校内の性暴力を描いた作品『言えないことをしたのは誰?』(現代書館)の著者・さいきまこさんのトークイベントを開催。"当日は、訪れる誰もが安心して過ごせる場所、語れる場所でありたいと思っています。これまで関心はあれどなかなか話す場所や相手がいなかった、という方にもご参加いただけたら嬉しいです。"『言えないことをしたのは誰?』は学校の性暴力をテーマに、小さな違和感から丁寧に描き、なぜ起き続けてしまうのか、どうすれば防ぐことができるのかというところまで切り込んだすごい作品でした。子どもと関わる大人たちにはどうかどうか読んでほしい。
☕️AFTER TALK
肩に負担がいかないようにしていたら腰に小さな痛みが来るようになって来ました。接骨院通いも「時間がない」を言い訳に頻度が減っていたので、週1以上は必ず行くようにしたいと思います。(先週行けていない……。)
それでは、まだまだ大変な世の中ですが、好きな飲み物を飲んで、ご自愛しつつ、今週もそれぞれの読書時間をお過ごしください。
#NOW READING 『地元を生きる』(小松理虎 / 筑摩書房)
すでに登録済みの方は こちら