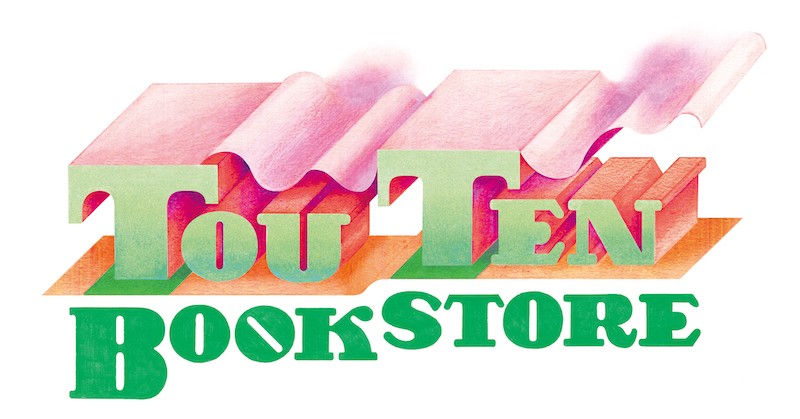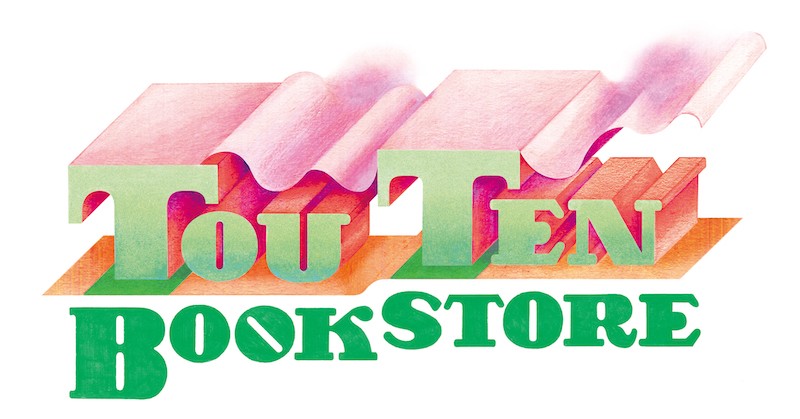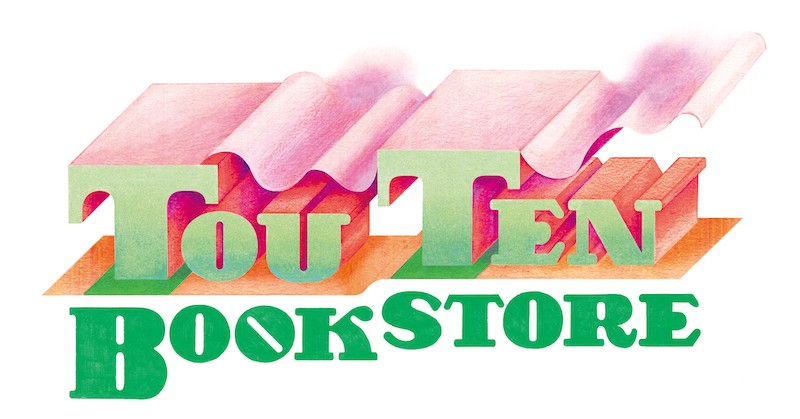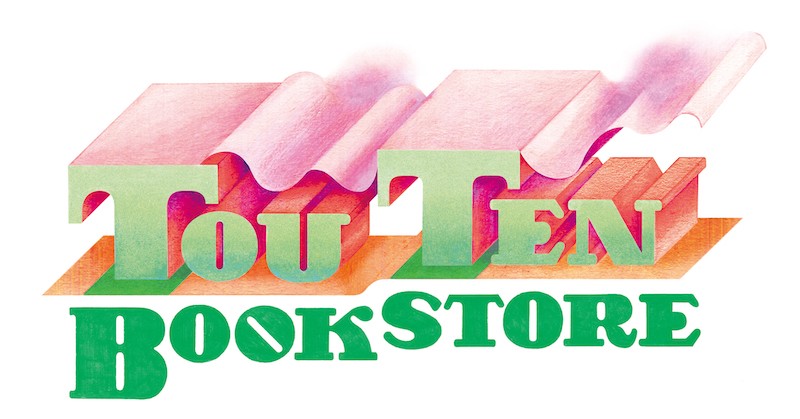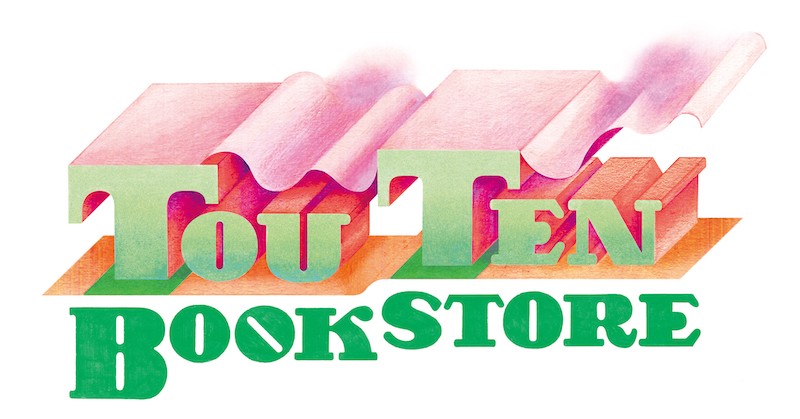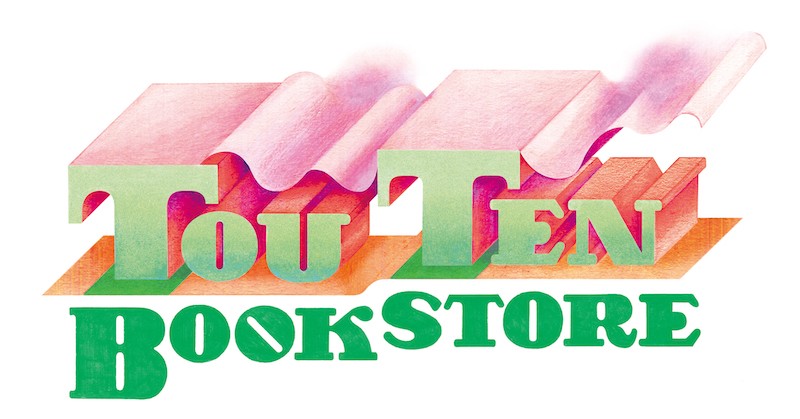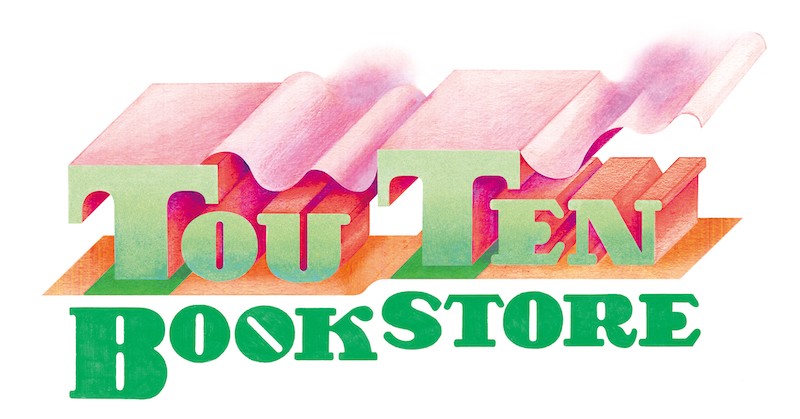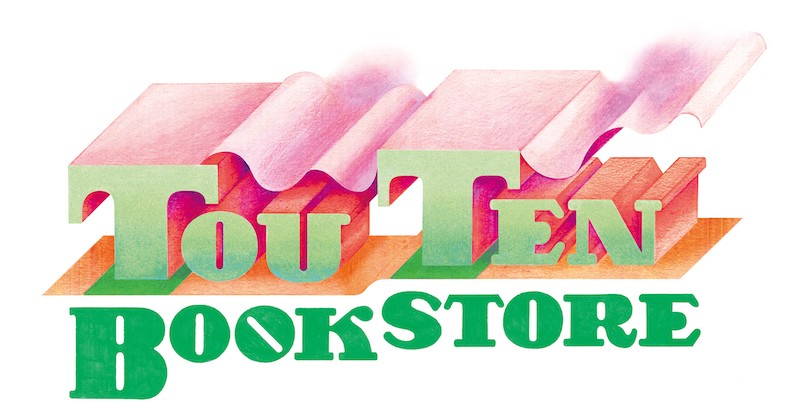TOUTEN BOOKSTORE NEWSLETTER #78
#78 INDEX
-
HELLO
-
TOUTEN ベスト (2025.3.3-2025.3.16)
-
新入荷&今週の1冊
-
イベント情報
-
AFTER TALK
☀️HELLO
2024年度の確定申告を無事終了できて本当にホッとしました……。今年はイベントや肩を壊すなどバタバタとしていて、ギリギリまでかかってしまった。精神的なストレスが少し緩和されました。
3/8は【「生誕100年 エドワード・ゴーリーの絵本たち あるいは翻訳のあとに」スピーカー:柴田元幸】がありました。ゴーリーの絵本が日本で出版されるようになったのは2000年、ゴーリーが亡くなった年なんですが、ゴーリーの生い立ち、やってきた仕事、受け継がれるゴーリーの世界観の話など、遡ってお話ししてくれました。なんと未刊行の朗読までしてくださり、とても贅沢な時間でもあり……。柴田さんのご厚意で550円でアーカイブチケットを販売していますので見逃した方はぜひこの機会に!
柴田さんがゴーリーに惹かれる理由として、社会が「こう」と決めているものから外れた視点を見せてくれる、という話(そもそも"意味"から解放されるための絵本もある)や、お客さんの質問タイムで書き手は何を伝えようとしているのか、という話の中で、それがわからないから作品にしている、という話はもう1時間延長したいくらいの話でした。
ゴーリーの絵本では有名な、『ギャシュリ-クラムのちびっ子たち』という、子どもたちの名前のアルファベット順にその子が死ぬ瞬間を淡々と描いていく怖い絵本があるのですが、これは、子どもという存在は当たり前に、大人よりも死の危険が近いというのがあり、その死をあるがままに描いているように思えます。色々な研究者がゴーリーの絵本について推測している中、あの表紙が地蔵菩薩ではないかという話にもなんだか納得してしまう……。他の人はどう思うのか、聞きたくなりました。
3/15に開催した「TOUTEN CINEMA CLUB」もすごく面白くて、また別で書きたいと思います。
📚TOUTEN BEST (2025.3.3-2025.3.16)
・AHIRU LIFE. AHIRU LIFE. 2 AHIRU LIFE. 3 (SANAE FUJITA / よはく舎)
1階にて開催中の『ORDINARY AHIRU LIFE.』。1~3まで出版されている作品集です。本日より、AHIRU LIFE.さんの作品の通信販売がスタートしています!絵とキャプションを見るだけでも『AHIRU LIFE.』の世界観が伝わると思います。人と比べてしまってどうしようもなく辛い時や、忙しすぎて追い詰められてしまっている時、AHIRUの世界がユーモアを持って癒してくれます。
・湯気を食べる(くどうれいん / オレンジページ)
オレンジページの連載の書籍化ということで、「たまご丼」のエッセイがこちらから読めます。"(あーあ)と思うくらいのごま油"で伝わるものがあるの、すごいなあと思う。私は最近台所のカウンターで立ちながら朝ごはん(味噌汁と納豆ごはん)をサクッと食べるのが好き。
・私が私らしく死ぬために 自分のお葬式ハンドブック(rn press=編 / rn press)
"最新の遺体処理から安楽死まで。あなたは、いつ、どこで死ぬでしょう。よりよく生きるために知っておきたい「死ぬ」ということ。"入荷してすぐ売れ、追加分もまた売れた本書。rn pressの野口理恵さんのZINEが書籍化したもの。岐阜・本の市に行った時rn pressのブースがあったのですが、(古書市を眺めすぎて)時間がなくなってしまい……色々お話聞きたかった!!!
・らせんの日々(安達茉莉子、社会福祉法人 南山城学園=取材協力 / ぼくみん出版会)
『私の生活改善運動 THIS IS MY LFE』の著者・安達茉莉子さんが誰もが人間らしく生きることができる世界を目指す「福祉」の現場を書く。上から見れば、堂々めぐりのように見え、横から眺めれば後退しているようにも見える。でも、踏み出した一歩によって、わずかに、高みへと上がっている。そんな“らせん”のような日々を、福祉の現場ではたらく職員の語りを通して描いたエッセイ。
・ビジネスと人権(伊藤和子 / 岩波書店)
私たち一人一人が国連の「指導原則」が示す「ビジネスと人権」の発想を知り、企業風土や社会を変えるための一冊。資本主義がパワーを持ちすぎて、人権が蔑ろにされているビジネスは散見されるわけで、今読むべきな1冊だと思います。
📚新入荷&今週の1冊
・RITA MAGAZINE2 死者とテクノロジー(中島岳志=編 / ミシマ社)
AI時代、人類だけが行ってきた「弔い」はどうなる?葬式、墓、仏壇、失われる弔いの伝統と、台頭するAI故人ビジネス。そのリスクと可能性を、情報学、文学、宗教、政治学…多方面から考察する。執筆陣:中島岳志/高木良子/ドミニク・チェン/平野啓一郎/高橋康介/佐々風太/松尾公也/古田雄介/パトリック・ストークス/西出勇志/谷山昌子/池口龍法
・石垣りんの手帳 1957から1998年の日記(石垣りん / katsura books )
戦後女流詩人の草分け的存在である石垣りん。生誕100年を経て没後20年を迎える現在も、石垣りんの詩やエッセイは人々の心のひだに触れてくる。katsura booksの織田さんが当店にいらした時に初稿を見せてもらったのですが、手帳の中身がそのまま本になっていてたまげた。本の形になったらまた佇まいが素敵すぎて……。本人の書いた文字がそのままだと、その人の生を感じるよう。
・Monthly Newsletter Column May 2023-February 2025(FIFTYS PROJECT / 一般社団法人NewScene)
政治分野のジェンダー不平等を今の世代で解消するために20代・30代の女性(シス/トランス)、Xジェンダー、ノンバイナリーの地方議会議員への立候補を呼びかけ、一緒に支援するムーブメント「FIFTYS PROJECT」のZINE。フェミニズムのスローガンである「個人的なことは政治的なこと」をベースに、この社会に存在する一人一人の声を拾い上げる構成になっています。
・本をともす(小谷輝之 / 時事通信出版局)
梅屋敷・葉々社の小谷さんが本を開業するまでと本屋が開業してからの実績まで載せた1冊。小谷さんは元々出版社の編集をされていて、"待つ"ことが嫌じゃなかった。お店も基本的には"待つ"ことが多いから本屋は性に合っていた、というような話にホクホクする。当店の名前も出てきて嬉しかったです。開業前はよく来店してくださってて、いろんな話をしました。懐かしい。
\📚今週の1冊📚/
3/16付の中日新聞の「書店員の一冊」欄に寄稿しました。一見どんな本?!となると思うんですが、同時代を生きる二人の対話と往復書簡をまとめた1冊で、今の地球に住む人間の一人として、現代社会を生きていく上で、示唆に富んだ本です。グイグイ読みました。"公害、戦争責任、消費社会といった大きなテーマについて、それぞれのフィールドを出発点に複雑さをまといながらもつなぎ合わされる言葉に、社会について立ち止まり考えるためのヒントが詰まっている。"と書きました。(一部抜粋)
個人的には、ゴッチ(ついゴッチ呼びしてしまう)が「社会的な発言」と「政治的な発言」の違いについて話していて、それだけでも読めてよかった〜!と思いました。ある問題が起きた時に解決するための行動として、外部に向けて発信することと、内部に向けて調整していくことは違うアプローチであって、どういうプロセスを踏んでいくのかを考えていくべき、というのは今の自分にとって靄が晴れるような話でした。
👀イベント情報
【🎫アーカイブ配信中!🎟️】
【展示】
1F展示情報【25.3.7-29】『ORDINARY AHIRU LIFE.』
言葉のないショートストーリーAHIRU LIFE.の巡回展です。「なんでもない日常に、ごく自然な態度でそこにいるアヒルたち。彼らのさりげなさをゆったりと味わってください。」


今年、生誕100年となるエドワード・ゴーリーの絵本は、この25年間ほぼ毎年刊行を続けて合計30冊以上となりました。ゴーリーの絵本や、貴重な輸入雑貨を並べています。石けんや『ギャシュリークラムのちびっ子たち』ポスターはすごく手に入りづらいのだそう。ぜひこの機会にゴーリーの世界をのぞいてみては。
【イベント】
イベント【25.3.29】🇵🇸PALESTINEハンドメイド部🇵🇸
主催はジェンダー読書会なごやさん。パレスチナに連帯するアクセサリーブランドRÉSISTIQUE さんのメタルパーツを使ってアクセサリーを作ります。ピアス、キーホルダー、チェーン、ビーズなど各種加工のためのパーツや工具を用意しているので、手ぶらで参加OK👌参加はリンクよりチェックをお願いします。
☕️AFTER TALK
「ノー・アザー・ランド」を観てきました。観られること自体が重要である映画なので、気になっていた方、知らなかった方もぜひ。4/4~は刈谷日劇でもやるみたいです。
ヨルダン川西岸のパレスチナ人居住地区「マサーフェル・ヤッタ」では、イスラエル軍による破壊行為と占領が進行していて、その記録をおさめたドキュメンタリーです。
ここからは内容に言及します🙏
イスラエル軍がマサーフェル・ヤッタを射撃演習場にすると宣言し、住民が起こした裁判は1999年から20年以上続いていました。2022年にはイスラエルの最高裁がパレスチナ人約1000人を立ち退きさせる判決を下しています。ずっと住んでいた住民がいるのは明らかであるのに、国際法違反であるのに、イスラエルの法律によって、「ここはパレスチナの土地ではないから」と理由づけ奪う、その暴力性。
住んでいた家が破壊される様子、平和的デモにも攻撃する様子、抵抗した市民が武装兵に撃たれる様子、入植者の暴言・暴力など、ショッキングな映像が続きます。住民が建てた学校が壊されるシーンは特に苦しかったです。
この映画は主に4人で作られていますが、監督でありながら、マサーフェル・ヤッタ出身のパレスチナ人・バーセルとイスラエル人・ユヴァルの二人は画面に映し出されます。軍法のもとに生まれ移動制限のあるバーセルと、民法のもとで生きて自由に移動もできるユヴァルの非対称性から生じる二人の会話に胸が苦しくなります。未来の話をすることができないバーセルと、未来の話を考えようというユヴァル。所々で浮き彫りになるバーセルの逃げ場のなさを切実に描いていて、苦しいし、"国"の暴力に腹がたつ。
イスラエル軍の「法律で決まっているので」の姿勢に「なんなん?」って思ってずっと観てたんですけど、イスラエル兵の視線とか本当に冷酷で、「実際どう思ってるのかな」と気になってきた中、印象的なシーンがあって。破壊行為を収めるためイスラエル兵にカメラを向けるユヴァルに対してあるイスラエル兵が「"敵"の味方につくなんてSNSでボコられるぞ」みたいな(←びっくりしすぎてセリフが全然思い出せないんですが"敵"と訳されていたのは覚えている)すごい暴言を吐くシーンがあって、このイスラエル兵にとってはパレスチナ人は「敵」であると教育されているんだ、と気が遠くなりました。「敵/味方」というものの見方には、本当に警戒しなければならないと感じます。線を引くことで、人間扱いしなくなること、攻撃していい対象とすること。だれもが尊重され生きる世界というのはこうも難しくされているのかと途方もない気持ちになります。
もう一度。観られること自体が重要である映画なので、気になっていた方、知らなかった方もぜひ。4/4~は刈谷日劇でもやるみたいです。→公開情報
ミリオン座で観たのですがパンフレットが最後の1冊でした。読みたい方いたらレジに置いておきますのでお声がけください。(補充されているといいな。)
それでは、まだまだ大変な世の中ですが、好きな飲み物を飲んで、ご自愛しつつ、今週もそれぞれの読書時間をお過ごしください。
#NOW READING 『三ギニー』(ヴァージニア・ウルフ、片山亜紀=訳 / 平凡社)
すでに登録済みの方は こちら